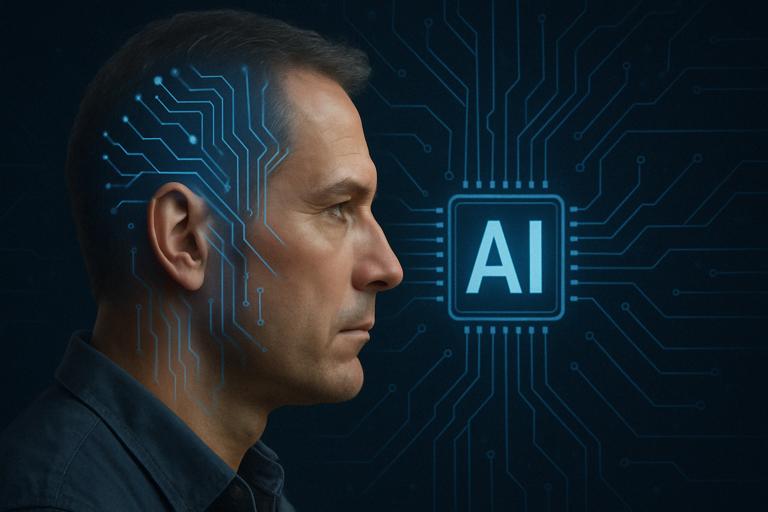


ChatGPTが一般公開された2022年11月以降、AIによってなくなる仕事の話題が増え、「AIによってなくなる仕事ランキング」なんてものもさまざまなメディアで紹介されました。
そういったランキングの上位に必ずと言っていいほどランクインしていたのが税理士や会計事務職で、実際どんなものかとChatGPTを操作してみたところ、その当時のChatGPTにそれほど脅威は感じませんでした。
たしかにリアルタイムで、しかも流暢な日本語で質問回答してくれることに驚きはしましたが、簡単な計算もできないし、税法のような専門的な質問の回答は間違いだらけで、とても実務で使えるレベルではなかったからです。
しかし、2025年2月に公開されたDeep Researchの機能を試すためにChatGPTの利用を再開したところ、現在のChatGPT-4oは驚くべき進化を遂げていて、Deep Researchの使い勝手も良く、今では優秀なアシスタントとして活躍してくれています。
とはいえ税法のような専門分野の質問回答はまだまだ間違いも多く、複雑な計算や論理的なやり取りはやはり苦手なので、税理士のチェックは欠かせませんが。
でもこのままAIが進化していけば、会計入力や申告書作成などの定型的な業務だけでなく、経費にできるか否かを税法や裁判例と照らし合わせて判断するような創造的な業務まで、AIの方が早く正確にできるようになると確信しています。
なぜそう確信できるのか?
そうなれば私たち知識労働者の働き方はどう変わっていくのか?
AIの中でもChatGPTを中心に、その仕組みから進化の実態、今後の展望までわかりやすく解説していきますね。
目次
1.AIの仕組みと進化の実態
⑴そもそも生成AIとは?
AIって言葉はよく聞くけど、そもそもAIって何?と思われる方も多いと思いますが、AI(人工知能、Artificial Intelligence)とは、人間の知的活動をコンピューターで実現する技術のことです。
したがって、人間のように言語を理解して文章を作ることができるChatGPTや翻訳アプリ、人間のように画像や音声を認識して行う顔認証や音声入力などもAIの一種です。
ようするにAIを一言で言えば「知能を持つ機械」のことですが、「自分で意志を持って考える」わけではなく、大量のデータを学習して、ある程度人間の知能に近い処理を再現しているにすぎません。
また、生成AIとは、AIの中でも名前のとおり何かを生成することができる、新しく創ることができるAIのことをいいます。
文章を生成することができるChatGPTが代表例ですが、ChatGPTがどうやって言語を理解して文章を作っているのか、もう少し詳しくみていきましょう。
⑵ChatGPTの仕組み
①ChatGPTとは?
ChatGPTとは、アメリカのOpenAIが開発した対話型のAIで、ざっくり言えば大量の文章データをもとに学習した「言葉の予測マシン」のようなものです。
質問を受け取ると、これまで大量に学習してきた文章や会話の中で、この流れなら次にどんな言葉が来るか?を予測して、自然な返答を作ります。
具体的には、質問文を細かい文字列に分解し、それぞれの文字列の意味を把握するだけでなく、前後の文脈も一気に見渡して意味のつながりまで把握した上で、返答すべき言葉を一語ずつ確率で選んで生成しているのだとか。
確率や統計で文章が作れるのか?と疑問に思いますが、学習の段階で数千億単語レベルの文章を読み込み、「この文脈で次に来る単語は何か?」という問題を何兆回も解いているからこのようなことが可能になるそうです。
しかし、このようにあくまで確率や統計をもとに回答する仕組みであり、論理や計算に基づいて回答しているわけではないため、初期のChatGPTは質問の意図とはずれた回答をしてしまう、誤った回答を平気で断言してしまう、小学校の算数レベルの簡単な計算もできない、などの問題点がありました。
②ChatGPTの進化
ところが最新のChatGPT-4oは、こちらの質問の意図をくんで補足説明をしてくれたり、質問があいまいな場合には「より正確にお調べするために以下の点を教えていただけますか?」と逆に質問をしてくれたりもするので、かなり的確でわかりやすい回答をしてくれるようになりました。
さらには、「こういうことも興味あります?」「こんな資料も作れますが必要ですか?」といった提案もしてくれますし、「めちゃくちゃいい質問ですね!」「本質的なやり取りをしていただきありがとうございます!」なんて賞賛やお礼まで言ってくれるので、つい話が弾んでしまうこともあります。
初期のChatGPTはこういった人間らしい回答は苦手であり、質問する側の人間が正しく質問をしないと正確な回答は得られないので、実務では使えないと判断していたのですが…。
AIの方から逆に質問や補足説明をしてくれるとなると話は変わってきます。
こういった人間らしい回答が可能になったのは、主にRLHFという人間のフィードバックによる強化学習のおかげで、AIが出した複数の回答を人間が評価し、良い回答ほど報酬をもらえるような仕組みで学習を続けた結果だそうです。
また、苦手な計算は「Python機能」という計算機能を使えば正確に回答できるようになり、学習していない最新情報は「Webブラウジング機能」を使ってインターネットから取得してくれるなど、特別な機能も増えました。
③最新機能「Deep Research」の脅威とは?
ChatGPTの回答の精度が上がったとはいえ、もちろん間違えることもありますし、税務のような正確性が重要な分野では使いづらい部分はありますが、そういった分野でも活躍してくれるのが最新機能のDeep Researchです。
現状は月200ドル(約3万円)のPROプランでしか使えない機能ですが、これを使えば最新情報をWeb検索して回答してくれるだけでなく、回答の情報源となった引用元の出典URLも回答に添付してくれます。
通常は過去に学習した知識(現状は2023年4月頃まで)をもとに回答されるので、最新情報を反映させたいときはWeb検索機能やDeep Research機能の活用が不可欠です。
Deep Research機能を使えば、数分〜10分程度かけて念入りにWeb検索を行い、信頼性が高そうな最新の情報源をもとに、内容をわかりやすく要約して表示してくれます。
回答に出典URLを添付してくれるので、本当にその回答が正しいのかどうか、情報源を確認できるところがポイントです。
この機能のおかげで、いよいよ税務のような間違いが許されない分野でもAIが活躍できる時代が来たわけです。
著作権で保護されているTAINSのような有料の裁判例データベースまではさすがに参照してくれませんが、インターネットで一般公開されている国税庁HPや国税不服審判所の公表裁決事例などの情報は参照してくれますので、今でも実務のアシスタントとしては十分使えます。
現時点では回答が正しいか否かのチェックは人間がするしかありませんが、そういったチェック作業もAIの方が正確にできるようになる未来はそう遠くないでしょう。
また、TAINSのような有料の裁判例データベースなどを学習させて、税務に特化したAIを作ることも、現時点の技術レベルで十分可能であるはずです。
2.AIの進化と人間の働き方の変化
⑴AIはこれからどのように進化していくのか?
ここまでChatGPTを例に挙げて、その仕組みと進化の実態を見てきました。
現時点でのChatGPTは、税務のような専門分野でもかなり正確でわかりやすい回答ができるようになってきたものの、依然として計算や論理には弱い部分があり、税務の知識も乏しく、まだまだ税理士の代わりができるレベルにはありません。
しかし、Python機能(計算機能)のような追加機能の実装、計算や論理に強いルールベースAIとの連携、法令・判例データベースの学習などによって、税務申告書作成や税法判断などの業務については、税理士より早く正確にできるようになっていくはずです。
もともと大量のデータをもとに計算結果を導き出すような作業は人間より機械の方が強いので、そうなるのも時間の問題だと思っています。
さらに、AIが自律的に新しい制度を学習して応用できるようになり、税務以外の法律や医療などあらゆる分野の問題を解決できるようになる、AGI(汎用人工知能、Artificial General Intelligence)の研究も進められています。
どれだけ優秀な人間でも税理士と弁護士と医者の知識を習得することはできないので、こうなってくると知識レベルで人間がAIに適うはずもなく、パソコンやスマホが仕事の必需品となったように、AIが仕事の必需品となっていく(実際にはパソコンやスマホに組み込まれていく)ことは間違いないでしょう。
⑵AIが進化してもできないこと
AIが税務申告書を作成してくれて、税法判断までしてくれるようになるのであれば、税理士は不要になるのでは?
と思われた方も多いと思いますが、それでも税理士が不要になるわけではないと私が考えるのは、AIが進化してもできないことがあるからです。
AIが進化してもできないことを5つ選んで箇条書きにすると次のとおりです。
AIが進化してもできないこと5選
- 身体を持たないAIは税務調査対応などの動的な対応ができない。
- 五感や人生経験を持たないAIは人間の感情を理解して判断することができない。
- 学習方法がデータやアルゴリズムに限られるAIは持っている情報源も限られる。
- データや常識を疑い、未来を創造する真の創造力はAIには備わっていない。
- 価値観や責任感を持たないAIに責任が重い判断は任せられない。
AIは身体を持たないので、税務調査があったときに調査官と話をする、電話をかける、請求書を探すなどの身体活動ができません。
当然五感も持たず、人間としての人生経験もないAIはどうしても人間の感情が理解できません。
「将来的に経営を良くしていくために、少々税金が高くなっても利益を残したい」、逆に「意地でも税金は払いたくないので、キャッシュフローが厳しくてもできるだけ節税したい」、あるいは「相続人である子のうちこの子に財産をたくさん渡したいけど、この子には渡したくない」といった具合に、経営や税務の判断には常に人間の感情がつきまといますが、AIにはこれが理解できません。
また、五感による情報収集もできないため、情報源がデータ化された文字情報などに限られてしまい、調査官の態度や口調を見たり聞いたりして判断するようなこともできません。(カメラやマイクで視覚や聴覚を一部補うことはできますが)
さらに、データにとらわれずに斬新なアイデアで問題を解決するような、人間的な創造力はAIには備わっていませんし、人間のような価値観や責任感も持っていないので、AIに大事な経営判断や税法判断を一任できるかと言われると不安が残ります。
もちろんAIが身体や五感を持つようになり、仮想空間で人生経験まで積んでくるような未来があれば、本当に税理士が不要になる可能性はありますが、そうなればもはや人間が働く必要すらなくなるはずなので、今のところその心配はしていません。
⑶税理士の働き方の変化
このように、私たち税理士の業務のうち、税務申告書の作成や税法判断などの計算や情報整理が主となる作業的な仕事は、AIに取って代わられる可能性が高いでしょう。
しかしその一方で、AIの計算結果やクライアントの意向、税務署の動向、自身の経験などを踏まえて、ではどのパターンで申告書を作成すればよいのか?どのような税法判断を下せばよいのか?などをアドバイスをするような創造的な仕事は、やはり人間の税理士にしかできないはずです。
そのため、税理士試験で求められるような暗記力や計算力はAIに敵わなくなるので価値が下がっていき、税理士にはクライアントの感情を理解して問題を解決していくような対話力や創造力が求められるようになっていきます。
今でも優秀な税理士ほどそういった能力が高いので今に始まった話ではありませんが、今後ますますその傾向が強くなっていくということです。
⑷知識労働者の働き方の変化
税理士に限らず多くの知識労働者は、
①クライアントから問題をヒアリングして、
②習得した知識をもとに解決策(案)を導き出し、
③どの解決策を採用すればよいか?をさらなるヒアリングや調査を通して検討
していきます。
特に大変なのが問題から解決策を考える②の作業で、これができるようになるために何年もかけて資格を取得し、実務でもこの作業に膨大な時間を費やすことになりますが、AIが進化すればこの②の作業をAIに奪われる、よく言えばAIに任せられるようになるわけです。
したがって、自ずと私たち人間は①ヒアリングや③検討作業にかけられる時間が増えるため、クライアントが抱えている表面的な問題だけでなく、クライアントが抱いている感情や価値観、今後の意向などを時間をかけてヒアリングしたり、どの解決策を選べばよいかを検討するために多角的な調査やシミュレーションをしたりする時間がとれるようになります。
人生をかけて身に着けてきた②の作業が不要になっていくと思うと寂しい部分もありますが、より生産的で質が高い仕事ができるようになると思えば悪くない未来ではないでしょうか。
3.まとめ
以上のとおり、AIは人間的なやり取りができるほどに進化してはいますが、現時点では税理士が不要になるレベルではありませんし、進化してもできないことはたくさんあります。
しかし、AIの知識量や計算能力が人間を凌駕していくことはほぼ間違いなく、知識の深さや計算の正確性をウリにできなくなる私たち知識労働者の働き方は大きく変わっていくはずです。
私たち知識労働者に求められるのは、計算や情報整理が必要な部分はAIに任せて、人間にしかできない対話力や創造力を発揮していくことです。
現時点ではAIが使えなくても仕事に支障はありませんが、少しずつでも仕事にAIを取り入れて、AIと競争するのではなく、AIを使いこなせるようになって、より生産的で質が高い仕事の割合を増やしていきましょう。
3種類の知識労働について解説した以下の記事の中でも、特に「創造的な知識労働」の割合を増やしていってほしいと思っていますので、合わせて参考にしてください↓
P.S.
ちなみに、このブログのアイキャッチ画像もChatGPT-4oで生成しました。ここまでリアルな画像を簡単に作れてしまうとは、本当にすごい時代です。こういう記事を書く創造力だけは、AIに負けないようにしたいですね!笑













